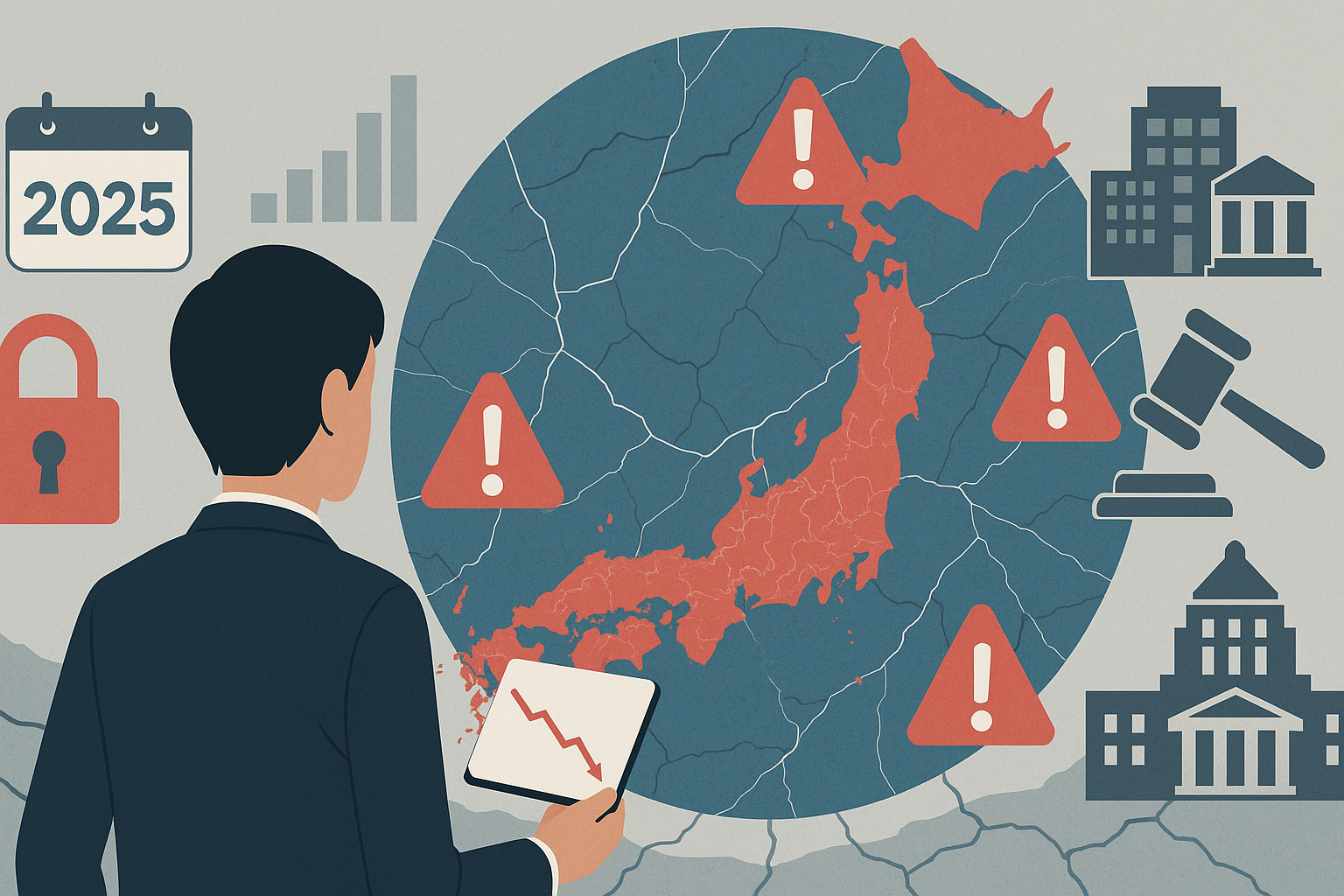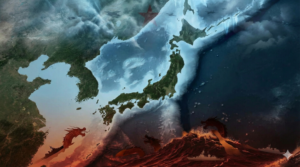AIと人間がともに語る「国家の未来」。2025年の日本は、エネルギー・食料の輸入依存、少子高齢化、財政赤字、地政学リスク、サイバー空間の脆弱性など、複合的なリスクに直面しています。こうした課題を可視化し、打ち手を見出すために、OpenAIのChatGPTとGoogleのGeminiという2つのAIを活用し、「ヒト×AI討論」というかたちで多面的に考察を深めました。
#5では、2つのAIが導き出した問題認識と提案内容の共通点と相違点を整理し、人間の視点を交えながら、国家戦略の新たな構想を描きます。AIの冷静な分析と、ヒトの経験知と責任感。それらを融合させた“未来への対話”を、ここに記録します。
(これまでの「ヒト×AI討論」)
【ヒト×AI討論003】2025年の日本に潜む脆弱性と制度改革の提言 #1 – 賢慮の学校
【ヒト×AI討論004】2025年の日本に潜む脆弱性と制度改革の提言 #2 – 賢慮の学校
【ヒト×AI討論005】2025年の日本に潜む脆弱性と制度改革の提言 #3 – 賢慮の学校
【ヒト×AI討論006】2025年の日本に潜む脆弱性と制度改革の提言 #4 – 賢慮の学校
2つのAIの共通点:AIが導き出した「構造的弱点」
まず目を引くのは、ChatGPTとGeminiのいずれも、日本の脆弱性を非常に整然と体系的に把握している点です。両者が共通して挙げた主なリスクは以下のとおりです。
- 少子高齢化とそれに伴う社会保障の圧迫
- エネルギー・食料の海外依存と供給リスク
- 財政赤字の累積と将来世代への負担転嫁
- サイバー・宇宙・情報空間での防衛力の弱さ
- 外交的中立を強いられる地政学的立場の危うさ
- 社会の分断と民主主義の劣化
特に「エネルギー・食料自給率の低さ」「人手不足と高齢化による国家の持久力の低下」「サイバーセキュリティと情報戦への脆弱性」の3点は、ChatGPTとGeminiともに「優先的に強化すべき領域」と位置付けています。
AIが示すこの一致は、「これらの課題はもはや異論の余地がない、避けては通れない本質的なリスクである」ことを物語っています。
2つのAIの相違点:分析アプローチの違いが見える
共通の問題意識を持ちながらも、ChatGPTとGeminiにはアプローチの違いが明確に現れています。
ChatGPTは、政策立案者の補佐官のように、「現行制度の課題分析→改善提案→予算と制度設計」という具合に、現実政治との接続性を重視しています。たとえば、出生率改善のために児童手当や教育無償化の拡充、再生可能エネルギー導入に向けた送電網整備、水素エネルギー政策の促進など、具体的な制度設計まで踏み込んで提案を展開しています。
一方Geminiは、ややメタ的・抽象的な視点から、「SWOT分析」「RCA(根本原因分析)」「PDCA/OODAといった改善フレーム」など、戦略理論や組織論のフレームを用いたアプローチに重きを置いています。国家を一つの“脆弱な組織体”と捉え、「弱点の特定→根本原因の分析→継続的改善による強化」という流れでレポートを構築しており、これは企業経営やプロジェクトマネジメントの文脈で使われる知見に近い思考法です。
言い換えれば、ChatGPTが「内閣府の政策スタッフのような視点」であり、Geminiは「外部コンサルタントのような俯瞰と抽象思考」が強みです。この対照性は、AIの利用目的に応じた“適材適所”を考えるうえでも示唆的です。
AIにない「歴史観」と「当事者性」
AIの回答はどちらも整然としており、非常に合理的です。しかし、どこか“地に足のついていない感じ”も否めません。そこで重要になるのが、ヒトとしての視点、すなわち歴史観と当事者性です。
まず歴史観。たとえば、エネルギーの海外依存や財政赤字といった問題は、今に始まったものではありません。オイルショックやプラザ合意、バブル崩壊、東日本大震災…。日本は過去にも何度も資源不足や制度の揺らぎに直面してきました。こうした歴史を学び直すことなくして、本質的な制度改革は語れません。AIはあくまで「データ」を起点とするため、歴史の“連続性”や“教訓”という文脈が抜け落ちやすいのです。
次に当事者性。AIは「政府はこうすべき」「制度はこう変えるべき」と述べますが、私たち一人ひとりが“国家の構成員”であるという前提が見えにくい。国家の持久力とは、結局のところ、「地域社会の強さ」「中小企業の底力」「家庭の自律性」に依拠しています。防災訓練、町内会、食料の備蓄、家庭の教育力──こうした草の根の努力なくして、どんな制度改革も絵に描いた餅に終わります。
まだAIにない「身体性」
ChatGPTやGeminiのようなAIは、情報処理や言語生成において極めて高い能力を持っていますが、まだ「身体」はありません。つまり、感覚を持ち、物理空間と相互作用し、摩耗し、制約に悩むという、人間にとっての基本条件が欠落しています。この“身体性の不在”は、AIがどれだけ高度な分析を行えても、「現場」や「実践」に基づいた判断や直感を持ち得ないという根源的な限界を意味します。
たとえば、災害時の避難行動、農作業や介護といった身体労働、あるいは日々の買い物や通勤の中で感じる社会の“肌感覚”。これらの実感をAIは持ちません。現実の日本社会では、制度や政策だけでなく、こうした身体的リアリティが意思決定に深く関わっており、それこそが「人間にしかできない判断」の源泉でもあります。
こうした限界を補う技術として、身体を持つAI=ロボティクスとの融合が注目されています。すでに災害救助用ドローンや介護補助ロボット、物流の自律搬送機器など、AIと身体を融合させた「実働型AI」の社会実装が進みつつあります。さらに、今後は身体性を持つAIエージェントが、農業、建設、防衛、地域見守りといった「人が現場に行く必要のある」領域において、不可欠な存在になっていくでしょう。
ここで重要なのは、ロボットやAIエージェントが人間に取って代わる存在ではなく、身体性の“代替”ではなく“補完”として共生する道を構想することです。人間が身体を通じて得る現場の直観、五感の記憶、他者との身体的共鳴──これらを補う役割をロボットが担い、AIがそれを学習・分析・最適化していく。こうした人間とロボットとAIの三位一体的な知性こそが、これからの日本社会の持久力を支える鍵となるかもしれません。
「ヒト×AI」の新しい国家戦略
ChatGPTの構造分析と政策提言、Geminiの戦略思考と内省的整理、そして人間の経験と責任感。この3つの知を組み合わせることこそが、これからの国家戦略の基本単位になるべきでしょう。
そのうえで、私たちが今こそ考えるべきは次のような問いです。
- 有事や災害に備えた複数シナリオによる国民的合意形成は可能か?
- 若者・女性・移民など「希望を持てる層」が生きやすい制度をつくれているか?
- 自律的に生き抜く力を支える教育・リテラシー政策は本気か?
答えはまだ明確ではありません。しかし、これらの問いをAIと共有し、対話し、試行錯誤を重ねていくこと。それこそが、未来の国家に必要な「賢慮」の営みなのではないでしょうか。賢慮の学校では、AIも含めた多様性ある対話を重ね、相手を慮る思考と行動による社会変容を推進します。