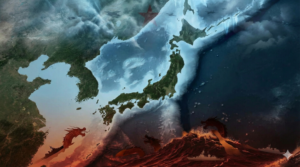これまでのキャリア選択は、学生・求職者が就職先を選び、企業が仕事を「与える」という流れが主流でした。しかし、しばしば「VUCAの時代」と呼ばれる環境変化が早く先の読めない複雑で不安定な環境の中で、テクノロジーの進化やグローバルな大きなうねり、社会の価値観の変化により、私たちの働き方も大きな転換期を迎えています。
こうした変化の中で注目されているのが「プロティアン・キャリア(Protean Career)」という概念です。これは、アメリカの心理学者ダグラス・ホールが提唱したもので、個人が環境の変化に適応しながら、自らの価値観や能力に基づいてキャリアを主体的に形成していく考え方を指します。従来の「会社に依存するキャリア」から脱却し、多様なスキルを活かしながら自分らしい働き方を模索する姿勢が求められています。
生成AIの普及やリモートワークの拡大、副業・複業の増加など、個人が自らのキャリアをデザインし、自分に合った働き方を選択できる時代が訪れようとしているのです。本稿では、人生100年時代と言われる現在で、これからの「ニューキャリア」の特徴と、職業づくりが新たな産業を生み出す可能性について考察します。
これまでのキャリア形成
かつて日本のキャリア形成は、「就職」ではなく「就社」という考え方が主流でした。これは企業に属し、その組織の一員として長期間にわたりキャリアを積み上げていくという雇用システムです。特に戦後の高度経済成長期以降、このモデルは日本の経済成長を支える重要な仕組みとして機能してきました。変遷を遂げつつも現在も基本の流れは続いています。
この雇用システムの特徴のひとつが、“メンバーシップ”型雇用です。これは、特定の職務に基づいて採用されるのではなく、「企業の一員」として採用される形態で、配属や異動を通じてさまざまな職務を経験しながら、企業内でスキルや知識を蓄積していくことを前提としています。新卒一括採用、年功序列、終身雇用といった日本企業独特の雇用慣行は、このメンバーシップ型雇用と密接に結びついています。
また、能力開発や教育訓練の内部化も大きな特徴です。企業が従業員の育成を自ら担い、長期的に人材を育てることで、組織全体の競争力を高めてきました。大手企業では入社後の研修プログラムが充実しており、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を通じて、業務の中で実践的なスキルを習得する仕組みが整えられていました。これにより、労働市場においては「即戦力」としての転職よりも、企業内でのキャリア形成が重視される傾向が強まったのです。
こうした仕組みは高度経済成長期(1955年-1973年)では有効で、大きな社会・経済環境の変化の中で企業が人材を引き付けるのに重要な役割を果たしました。
しかし、こうしたシステムには限界もあります。従業員のキャリアが企業内に閉じてしまうことで、外部労働市場での価値が低くなりがちである点や、柔軟なキャリア形成が難しくなる点が指摘されてきました。また、終身雇用を前提としたシステムが変化しつつある中で、従来のメンバーシップ型雇用が必ずしも最適とは言えなくなってきています。バブル崩壊以降、経済の長期停滞に伴い、企業が従来のような長期雇用を維持することが困難になり、成果主義の導入や雇用の流動化が進みました。また、人材育成への投資も年々減ってきました。
日本の実態は、宮川(2021)の推計によると、バブル崩壊後の1995年-1999年では、対GDP比0.41だったのに対し、年々低下し、2010年-2014年では0.1までに減少しました。
• したがって、日本企業の人材投資額(OJT以外)は、国内総生産(GDP)比で0.1%と、米国(2.08%)やフランス(1.78%)など先進国に比べて低い水準。
• アメリカ・フランス・ドイツ・イタリア・イギリスでは、GDPの1%以上を能力開発費として投資していますが、日本は0.1%程度。
• 日本の社外学習・自己啓発を行っていない人の割合は52.6%であり、諸外国と比較しても圧倒的に最も多くなっている。
半分以上の働く会社員が勉強していないのです。企業が人材に投資をしなくなり、自己啓発をしない人ばかりが増えたらどうなっていくでしょうか。
さらに、近年ではテクノロジーの進化やグローバル化の影響で、企業の枠を超えた働き方が注目されるようになっています。副業やフリーランスの増加、スタートアップの台頭など、企業に依存しないキャリアの選択肢が広がる中で、従来の「就社」モデルの変容を迫られているのです。
職業を自分でつくる時代へ
このように、かつては、学生たちは大学や専門学校等を卒業すると企業に就職し、その後は決められたキャリアパスを歩むのが一般的でした。しかし、現在の労働市場ではそのような固定的なキャリアの概念が急速に変化しています。企業がテクノロジーの進化とともに、生成AIやロボット・自動化が従来の仕事を一部代替する一方で、新しい職業やスキルが求められるようになっています。
これからの時代、仕事は「与えられる」ものではなく、自分で課題を見つけて「つくる」時代です。特に、若い世代は自らがどのような価値を提供できるかを考え、企業に依存せずに独自のキャリアを築いていく傾向が強まっています。このシフトは、職業選択の自由や自己実現の観点から見ても、非常にポジティブなものです。
他方で、会社に依存してきた社員にとっては、意識の変革とリスキリングが求められることになります。
このような背景の中で注目されているのが、「ジョブ・クラフティング(Job Crafting)」という考え方です。ジョブ・クラフティングとは、従来の職務記述書にとらわれず、個人が自らの仕事の範囲や方法を主体的に再設計し、やりがいを高める手法のことを指します。具体的には、業務内容の一部を自分の強みや興味に合わせて変えたり、周囲との関係性を見直して仕事の意義を再発見したりすることが含まれます。これにより、仕事に対する満足度が向上し、モチベーションの維持・向上が期待できます。
すなわち、自分自身の価値観と軸を振り返って理解し、個人が主体的に自らの仕事を再創造して、やりがいを高めていくことで、キャリアを切り開いていくことです。法政大学大学院 石山恒貴研究室とライフワークスの調査(「シニア人材”役割創造モデル”調査プロジェクト」、2019年)によれば、大企業で活躍する再雇用者と、その上司を対象に、何をしたのか?をインタビューし、そこから浮かび上がったのは次のような行動特性だったとし、活躍する再雇用者は、上手にジョブ・クラフティングをしていたと指摘しています。
• 再雇用者は、経験や意欲を踏まえて仕事の棚卸をし、上司と相談しながら、今の自分に適した仕事を自ら創造していく。
• 上司は、職務の切り出しや仕事のマッチングで支援し、一定程度の自己裁量を与えながら、再雇用者に適した仕事をアサインしていく。
また、この変化に適応する力として、「キャリア・アダプタビリティ(Career Adaptability)」の重要性も高まっています。キャリア・アダプタビリティとは、職業環境の変化に柔軟に対応し、自らのキャリアを主体的に発展させていく能力のことを指します。これは、単にスキルを身につけるだけでなく、自分の価値観や働き方の優先順位を見極めながら、新しい機会を積極的に創出していく姿勢にもつながります。
マーク・L・サビカスは、キャリア・アダプタビリティを、関心(Concern)、統制(Control)、好奇心(Curiosity)、自信(Confidence)の4つの次元で自分自身のキャリアについて考え、キャリア形成のために必要な行動ができる能力を身につけることが求められているのです。
このように、ジョブ・クラフティングとキャリア・アダプタビリティを活かすことで、個人は企業や市場の変化に振り回されることなく、持続可能なキャリアを築くことができるのです。
職業づくりが産業づくりにつながる
職業を自分でつくるという行為は、単なる個人のキャリア設計にとどまりません。それが積み重なれば、やがて新しい産業を創出する力にもなるでしょう。例えば、プログラミングスキルを持った個人が自らアプリケーションを開発し、スタートアップを立ち上げることで、新しい市場や雇用が生まれるという現象が既に広く見られます。
また、気候変動や社会的な課題に対する関心が高まる中で、新たなソリューションを提供するための職業やビジネスが次々と誕生しています。環境保護をテーマにした企業や、持続可能なライフスタイルを提案する仕事がその一例です。起業や創業が注目されるようになり、単なるベンチャーからスタートアップが一つの職業として認知されるようになりました。
東京大学をはじめ、多くの大学で学内起業する学生たちも増加しています。例えば、AI人材・組織の育成を支援するオンライン学習サービス「Aidemy」を提供している株式会社アイデミー。東京大学松尾研究室出身のエンジニア集団が設立し、日本語自然言語処理技術を活用したソリューションを提供している株式会社イライザ。IoT無線技術「UNISONet」を開発し、製造業や鉄道業界などでの監視・計測システムとして活用されているソナス株式会社。建設機械の遠隔操作サービス「Model V」を提供し、建設現場のDX・自動化を推進しているARAV株式会社。
さらに、東京大学研究室発のスタートアップとして注目されているのがDeepXです。DeepXは、産業用ロボットや重機などのオペレーションを自動化するAI技術を開発しており、労働力不足の解消や作業の効率化に貢献しています。特に、建設・製造・物流などの分野では、熟練作業者の高齢化が進んでおり、DeepXの技術はそれを補完する重要な役割を果たしています。同社は、東京大学工学系研究科の研究成果を活かしながら、AI・ロボティクス分野での社会実装を推進しており、日本の産業構造の変革にも寄与しています。
このように、職業を自ら創造することは、結果として産業全体を押し上げる要因にもなるのです。
企画力が求められる「新しい職業」の設計者
職業を自分でつくるには、もちろんスキルや知識が必要ですが、重要なのは「企画力」です。自らの強みを深掘りして理解し、市場のニーズと結びつけて新しい職業をデザインできる力こそ、これからの時代に求められる能力の一つです。
単に「職業を選ぶ」のではなく、「新しい仕事を提案する」ことが重要になります。個人が自身のアイデアを実行し、事業を展開するためには、マーケティングやビジネスモデルの構築といったビジネスの基本的なスキルも不可欠です。そのため、従来の教育機関でも、起業やプロジェクトマネジメントに関するカリキュラムが急速に広がっています。
同時に、こうしたことを支援したり伴走することのコーディネート能力も重視されています。起業経験者をロール・モデルとしたり、ハンズ・オンを前提とした投資家も出てきており、これらも一つの職業として成長していくことでしょう。
人生100年時代とVUCA時代のキャリア戦略
現代は「人生100年時代」と言われ、従来の「教育→仕事→引退」という三段階のライフモデルは崩れつつあります。同時に、変動が激しく、予測不能なVUCA(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)の時代を迎えています。このような環境では、長期的なキャリア設計が困難になり、柔軟な働き方やスキルのアップデートが必要不可欠となっています。
「ライフシフト」という概念が注目されているのも、この背景があるからです。ライフシフトとは、ロンドン・ビジネススクールの教授であるリンダ・グラットンが提唱した考え方で、人生100年時代において個人がキャリアを長期的に再設計しながら、新たな学びや仕事を通じて成長し続けることを指します。日本でもベストセラーとなった彼女の著書『LIFE SHIFT(ライフ・シフト)100年時代の人生戦略』では、従来の直線的なキャリアパスが崩れ、個人が複数のステージを経験しながら働き続けることの重要性が説かれています。
具体的には、キャリアの中で何度も学び直し(リスキリング)、新しい職業にシフトすることが求められる時代に突入しました。特に、テクノロジーの進化によって、従来の職業が消滅し、新たな職業が生まれるペースは加速しており、個人の適応力が試されています。たとえば、AIやロボティクスの発展によってルーティン業務が自動化される一方で、データアナリスト、AIエンジニア、エシカルデザイナーといった新しい職種が登場し、多くの企業が求める人材像も大きく変化しています。
このような環境では、一つの組織に依存するのではなく、「ポートフォリオ・ワーカー」として複数のスキルを活かしながら柔軟に働くスタイルが増えています。また、会社に雇われるだけでなく、フリーランスや起業、NPO活動など、多様な働き方が一般化しつつあります。ライフシフトを実践することで、個人は年齢やキャリアの枠にとらわれず、学び続けながら新たな機会を創出することができるのです。
人生100年時代におけるキャリア戦略は、「学び直し」と「適応力」が鍵を握ります。予測不能なVUCAの時代を生き抜くためには、単にスキルを磨くだけでなく、自分自身の価値観を定期的に見直し、新しい環境に柔軟に対応する姿勢が求められるでしょう。
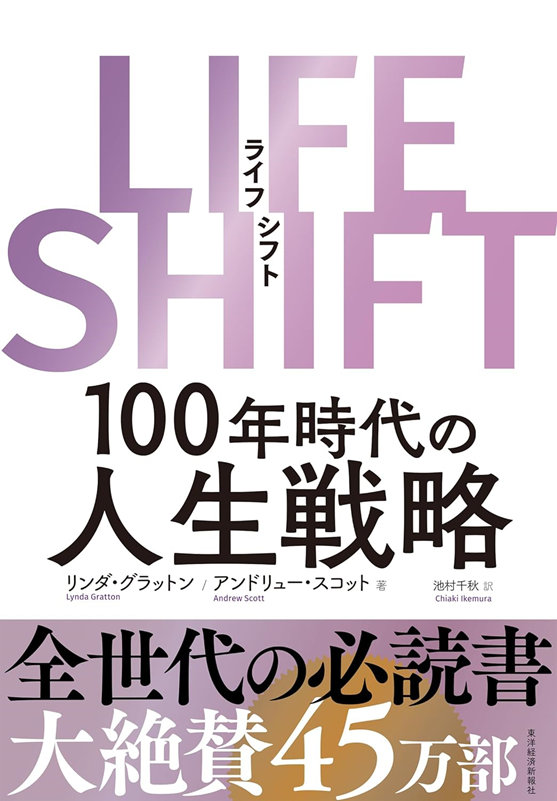
生涯学び直しの時代とリスキリングの重要性
このような変化の中で、キーワードとなるのが「アンラーニング&ラーニング(学び直し)」です。一度習得したスキルや知識が通用しなくなる場面が増えており、それを一旦手放し、新たに学び直すことが求められています。特にリスキリング(Reskilling)は、既存のスキルを更新し、新しい職業や働き方に適応するための重要なプロセスとなっています。
さらに、学び直しにはいくつかの種類があり、それぞれの概念を正しく理解することが重要です。
アップスキリング(Upskilling)
現在の職務や業界において必要なスキルを向上させ、より高度な業務を担えるようにすることを指します。例えば、マーケティング担当者がデータ分析やAIツールを活用するスキルを習得することがアップスキリングに該当します。
リスキリング(Reskilling)
まったく新しい分野のスキルを学び、異なる職種や業務に適応するための学び直しを指します。例えば、製造業で働いていた人がプログラミングを学び、ITエンジニアとして転職するケースがリスキリングに該当します。DX(デジタル・トランスフォーメーション)の進展とともに、多くの企業がリスキリングの重要性を認識し、従業員向けの教育プログラムを強化しています。
アウトスキリング(Outskilling)
企業が従業員に対して、現在の職場を離れた後にも活かせるスキルを習得させる取り組みを指します。たとえば、テクノロジーの進化によって業務が自動化され、職を失う可能性のある労働者に対し、新しいキャリアパスを支援するための教育を提供することがアウトスキリングの一例です。企業が従業員のキャリア転換を支援することで、労働市場全体の流動性が高まり、社会的な影響も軽減されます。
リカレント教育(Recurrent Education)とは、社会人が継続的に学び直しを行う仕組みを指します。これは、短期的なスキルアップにとどまらず、長期的に学び続けることを前提とした教育モデルです。例えば、社会人が大学や専門機関で学び直し、新たな分野でのキャリアを築くことがこれにあたります。リカレント教育は、単に個人のスキルアップにとどまらず、社会全体の競争力を高める役割も果たしています。
これに伴い、大学も「カルチャーセンター」的な役割にとどまらず、社会人が再教育を受けられる場としての機能を強化すべきでしょう。リカレント教育を推進し、労働市場の変化に対応できる人材育成が求められます。企業や教育機関、政府が協力し、学び直しの機会を広げることが、これからのキャリア戦略において不可欠な要素となっています。
(2)に続く。
参考・出典:
石山 恒貴「ジョブ・クラフティング ~ミドル・シニアの仕事の再創造~」 | 慶應丸の内シティキャンパス(慶應MCC)(2022)
『LIFE SHIFT(ライフ・シフト)100年時代の人生戦略』(リンダ・グラットン、アンドリュー・スコット 著 池村千秋 翻訳 東洋経済新報社 2016)